
新番組 私を啓く聖書のことば
雨宮 慧(カトリック東京教区司祭、上智大学神学部名誉教授)
10月14日(金)放送 第1回「十字架―父と子の栄光の交換とその新しさ」
使徒言行録14:21~27、ヨハネの黙示録21:1~5a、ヨハネによる福音書13:31~35
FEBC月刊誌2022年10月号記事より
・・・
福音を告げ知らせ、
多くの人を弟子にして
彼らを力づけ、励まし、
長老を任命した。
それゆえ、祈り、彼らを任せる。
彼らの主に。
私たちは見る。
新しい天と新しい地、
新しいエルサレムを。
私たちは聞く。
「万物を新しくする。」という御声を。
子は栄光を受けた。
父も子によって栄光をお受けになった。
父が子によって栄光をお受けになったのであれば、
父は子に栄光をお与えになる。すぐに。
だから、子は私たちに与えられた。
新しい掟を。
新しい掟―それは、互いに愛し合うこと。
「わたしがあなたがたを愛したように」
・・・
復活節第5主日の聖書から
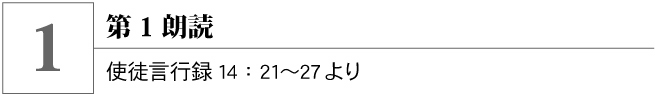
21 二人はこの町で福音を告げ知らせ
多くの人を弟子にして
リストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返した
22 弟子たちを力づけて
信仰に踏みとどまるように励まして
私達が…多くの苦しみを経なくてはならない
23 弟子たちのため教会ごとに長老たちを任命し
パウロ→信徒たち
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パウロ→神
断食と共に祈って
彼らが信じる主に彼らを任せた
ここは「第一回宣教旅行」と言われている箇所ですが、先ず21~23節の直訳を見てください。
原文ではこの箇所の動詞は、23節前半までは、いずれもパウロたちが信徒に働きかけた行為を表すのに対して、その後ではパウロの働きかけの方向が信徒たちから神へと切り替わっている。つまり「告げ知らせ、力づけて、励まし、任命する」が、神に「祈って、任せた」というわけです。建設されてから未だ間もない若い教会が気がかりなパウロは、力を尽くして教会に働きかけていたわけでしょう。しかし、人間の努力には限界があり、仕上げるのは神だ、とパウロは自分の行動の背後に必ず神の存在を意識しているのです。全ては、自分と共にいた神が行われたことなのだと。
同時にこの箇所の動詞は、下線で示した分詞形の後で、太字の主動詞が来る構造が繰り返されているのです。つまり、この箇所は人間の働きの背後にある神の働きが次第に明確になるように書かれているのだと思います。この宣教旅行の主役はパウロたちではなく、彼らと共にいる神なのだということです。聖書というのは、神の存在をとても強く意識している人たちの本なのです。

1 わたしはまた、新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。
2 更にわたしは、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ、天から下って来るのを見た。
3 そのとき、わたしは玉座から語りかける大きな声を聞いた。「見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、
4 彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。」
5 すると、玉座に座っておられる方が、「見よ、わたしは万物を新しくする」と言った。
ここではもの凄いスケールの世界観が打ち出されています。そのキーになるのは、ここで出てくる「新しい」(カイノス)という言葉です。そして、その意味は「古く時代遅れになったものが、新しいものに取って代わられる」ということです。
黙示録というのは、我々人間が生きている場所はどうにもならない悪がはびこっている場所で、人間がいくら頑張ってみても悪が存在しない世というのは無いと見ている。それ故に、黙示録は「新しいもの」が来ることを特に強調する。「新しい天と新しい地」、「天から新しいエルサレムが下ってくる」と述べているのです。そしてこの都は「万物を新しくする」神の新しい創造の中心となって、天と地を融合するものだと考えられています。
では、この新しさとは何であるのか。それは、同じカイノスという言葉が使われている「この杯は、あなたがたのために流される、わたしの血による新しい契約である。」(ルカ22:20)ということになる。つまり、キリスト者はイエスの血による「新しい」契約を信じ、「新しい」エルサレムを見る者だということなのだと思います。
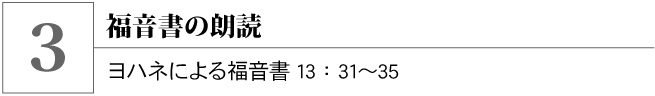
31 さて、ユダが出て行くと、イエスは言われた。「今や、人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。
32 神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神も御自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかも、すぐにお与えになる。
栄光の授受
別離の予告
新しい掟の授与
31~32節で「栄光を受ける」「栄光をお与えになる」と訳されているのはドクサゾーという動詞ですが、ここで5回も使われています。それにしても、イエスが十字架に上ろうとしているのに、その中で「栄光を受ける」というのは私たちには分かりにくい。加えて、「神も人の子によって栄光をお受けになった」と書かれています。これらは、イエスと神との関わりの深さがこういう言葉で言い表されている。言い換えれば、イエスと神との間に「栄光」が行き来しているのだという意味だと思います。このイエスと神との間の深い関わりの中で、34節で弟子たちに「新しい掟」が与えられる。つまりこの掟は、父なる神と子なるイエスとの間に交わされる、この栄光に支えられていると言えます。それを表すためにこの箇所は、31~32節の「栄光」の授受→33節の別離の予告→34~35節の「新しい掟」の授与という構造になっているのだろうと思います。
ですから、この「新しい掟」は単なる規則ではありません。「イエスが求めているもの」という意味なのだと思います。そして、このイエスの新しい掟が人を死に追いやることがないのは、35節で「わたしがあなたがたを愛したように」とあるように、イエス御自身が父から受けた掟、すなわち御自身の命を捨てて十字架に上ることを通して示されたもの—それは父なる神の愛だからです。
(文責・月刊誌編集部)
